 地区:静岡県菊川市 区間:堀之内駅前~池新田/14.8km 軌間:610→762mm/単線 動力:馬力→蒸気・内燃
地区:静岡県菊川市 区間:堀之内駅前~池新田/14.8km 軌間:610→762mm/単線 動力:馬力→蒸気・内燃
オットと呼ばれる先駆的な内燃機関車を使用していたことで有名な軌道。馬車鉄道からの格上げだが、その機関車の不調も要因に加わり、早々に廃止されてしまった。
なお馬鉄時代の軌間は二尺(しゃく)=606㎜として特許申請されたが、尺貫法を採用する可能性は皆無に等しく、文字の混同による誤記と捉えることが合理的で、実寸はのちの書類に記された二呎(フィート)=610㎜が正しいと考える。
略史
| 明治 |
32(1899) - |
8/ |
19 |
城東馬車鉄道 |
開業 |
| 大正 |
5(1917) - |
1/ |
28 |
御前崎軌道に改称 |
|
|
11(1922) - |
2/ |
8 |
堀之内軌道運輸に改称 |
(譲渡) |
|
12(1923) - |
12/ |
29 |
〃 |
全通 |
|
13(1924) - |
2/ |
28 |
〃 |
改軌・動力化 |
| 昭和 |
10(1935) - |
12/ |
7 |
〃 |
廃止 |
路線図
廃線跡現況
開業時の初代堀之内(写真A)は、駅前を東西に抜けていた旧県道南側に設けられ、隣接する本社、転車台等は廃止時まで使用されたようだ。新たに整備された駅前広場西側の店舗がこの一画に相当する。
客貨の便を図るため省線駅構内に乗入れた二代目堀之内駅前(写真B)は、その駅前広場に飲み込まれて面影はなく、東海道線側の駅名も既に菊川へと変わる。なお大正2年に鉄道院所有地から社有地に移転との書類もあることから、馬鉄の開業時はやはり当時の院線駅構内に置かれていた可能性が高い。
西向きに出発した列車はすぐ左に折れ、西通りと呼ばれる県道79号線(写真C)に合流する。
右手の市役所を過ぎると一旦住宅密集地内に入り込み、五丁目(写真D)からは県道37号線上の併用軌道として南下する。なお馬鉄時代の大正5年版地形図はここに直角クランクが描かれ、動力変更に伴い直線化されたと考えられる。書類上その変更区間は次駅付近までとされるも、同駅以南は現地での確認が難しい。
待避所のあった万田橋(写真E)を過ぎ、次いで東名高速をくぐり、けやき通りと合流したのちは両側に歩道が備わり道路幅が若干広がる(写真F)。道の東側を走っていたようだが、拡幅された現状からその面影を探し出すことは不可能に近い。
なお途中の各駅は地形図に記載がないため距離計測により位置を推定した。ただし当初は間(けん)単位だったことや、起点が変遷したこと等から、ある程度の誤差は織り込まざるを得ない。
続く三軒家(写真G)は場所が移動し、初代の20m程北が二代目となる。待避所も備えていたが、馬鉄時代は起点より1091間地点から30間二尺の間(1984-2098m)とされ、内燃化後の初代駅距離呈1哩15鎖50節(1921m)と若干のずれが生ずる。
駅の先で道路上を外れ専用橋で菊川(写真H)の旧河道を越える。当時は三軒家集会所付近を東西に横切っていたが、改修により新たな流路が開削され、橋梁痕は旧道路橋共々現在の道路下に隠されてしまった。
その後道路上に円通寺(写真I)、待避所を持つ西横地(写真J)と続くが、共にホームすらない停留所のため目印はなく、正確な位置の把握は難しい。
時刻表に載せられた土橋は距離が不明で、同名バス停があるものの他駅の例から置換られたとは考えずらく、おおよその位置すら把めない。
奈良野(写真K)は馬鉄時代、起点より2391間(4347m)地点から40間1尺の待避線があったとされ、同所の東側々溝に若干の屈曲、広がりが認められる。
さらに市道から県道37号線上に戻った路線は、上平川(写真L)を過ぎて牛渕川(写真M)を渡る。当河川も内燃化時に線路移設が行われたようだが、その後の河川改修により痕跡はきれいに消え去っている。対岸に渡ると旧道の路盤と思われる空き地(写真N)が現れ、このあたりで専用橋から併用軌道に戻っていたと考えられる。
この先に位置したのが待避所を持つ城山下(写真O)で、同名バス停付近に道路の膨らみも認められるが、前後駅との距離には若干の差異が発生する。
次の堤は時刻表に載るものの、やはり距離が不明なため場所を把握できない。
平田(写真P)は、待避所として複線用に広がった道路幅を今も明確に判別できる。当時の写真も公開され、正確な位置を特定できる初めての駅だ。
さらに橋本(写真Q)、赤土(写真R)と順に過ぎた後の虚空蔵(写真S)は距離呈を調べ切れず、駅名の元となったと思われる虚空蔵山福蔵院に近い、虚空蔵入口バス停付近かと推測するにとどめた。
馬鉄時代の終点南山(写真T)は、距離呈5哩65鎖と地番から南行の南山新町バス停付近と判断した。当初は道路外に設けられ、延伸時に若干移動した可能性もあるが、その詳細は判然としない。地形図に印された位置と大きく食い違う点も、疑問として残されたままだ。
以降の延伸区間は「数箇所の待避線を設け中間停留所とする」とされることから、後年追加された川原駅以外はすべて列車交換可能だったと考えられる。
次の南山学校前(写真U)は、まさに道路東側にふくらみが見られ、複線だったことを証明するかのようだ。
川原(写真V)は小笠高橋川の南岸となるが当時まだ川は開削されておらず、当然ながら橋梁痕は存在しない。むしろ地続きの至近距離に駅を設けた理由が興味の中心となる。
駅を出た後は左カーブを描きつつ市道上から離脱し、専用軌道として佐栗谷トンネル(写真W)に向かう。雑草に隠されてはいるが今も西側の煉瓦積ポータルを確認することができ、戦時中、軍の資材保管用に横穴が掘られていたこと、東坑口は道路側のトンネル工事により埋められたこと、等の話を地元で聞いた。
トンネルの先はあぜ道(写真X)が続く。既に元の所有者に戻され、今は私有地になっているとのこと。道路の終了と同時に民家内に飛び込み、右カーブで南に向きを変えたのち二車線道路に合流する。
この南方に置かれていたのが中尾(写真Y)だが、地形図位置とは若干の差異が認められ、駅名も同図、切符等には新野と印される。ここからは再び併用軌道に移行し、木ヶ谷(写真Z)以降は拡幅された県道37号線内に埋没する。しばらくして道路西脇に線路を移し専用軌道に戻るが、こちらも既に県道に取り込まれたと考えられ、浜岡球場の北となる大橋(写真AA)もこの中に含まれる。
県道242号線との交差手前に位置した、内燃化当初の終点苗代田(写真AB)。554ノ1番地とされることから、苗代橋南交差点南西に置かれていたようだ。
そのまま南下し計画段階の駿遠線に接続する予定を変更し、延伸区間は一旦、東に向ったため、二代目(同)は同交差点北西に移された。
新野川に接近すると、県道から右に一車線道路(写真AC)が分岐する。これが線路敷を転用した廃線跡道路となり、入口に「オットのみち」表示板(写真AD)が掲げられている。道路は一旦自動車販売店に突き当たって終了し、その先は未舗装の路地(写真AE)として再度現れる。写真左下にも表示板はあるが、残念ながら文字がはげ落ち、案内の役には立っていない。
 |
AD |
|
AE |
 |
| 18年9月 |
18年9月 |
路地を抜けた先が終点の池新田(写真AF)となり、今は民家が建ち並ぶ。車庫や転車台等を併設していたため、大きな構内であったことが偲ばれる。路線両端で転車台が必要とされたのは、オットと呼ばれる特殊なディーゼル機関車が、逆行運転を不得手としていたのかもしれない。
参考資料
- 鉄道ピクトリアル通巻330・331号/堀之内軌道/大庭正八 著 ・・・失われた鉄道・軌道を訪ねて
- 堀之内軌道運輸(二)・自大正十一年至昭和十年 他/国立公文書館
参考地形図
| 1/50000 |
 掛川 掛川 |
|
 御前崎 御前崎 |
|
|
|
|
|
| 1/25000 |
 掛川 掛川 |
[T5測図] |
 下平川 下平川 |
[S2鉄補] |
 千浜 千浜 |
[S2鉄補] |
 御前崎 御前崎 |
[S2鉄補] |
最終更新日2025-5/27 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*
転載禁止 Copyright (C) 2018 pyoco3 All Rights Reserved.


 地区:静岡県菊川市 区間:堀之内駅前~池新田/14.8km 軌間:610→762mm/単線 動力:馬力→蒸気・内燃
地区:静岡県菊川市 区間:堀之内駅前~池新田/14.8km 軌間:610→762mm/単線 動力:馬力→蒸気・内燃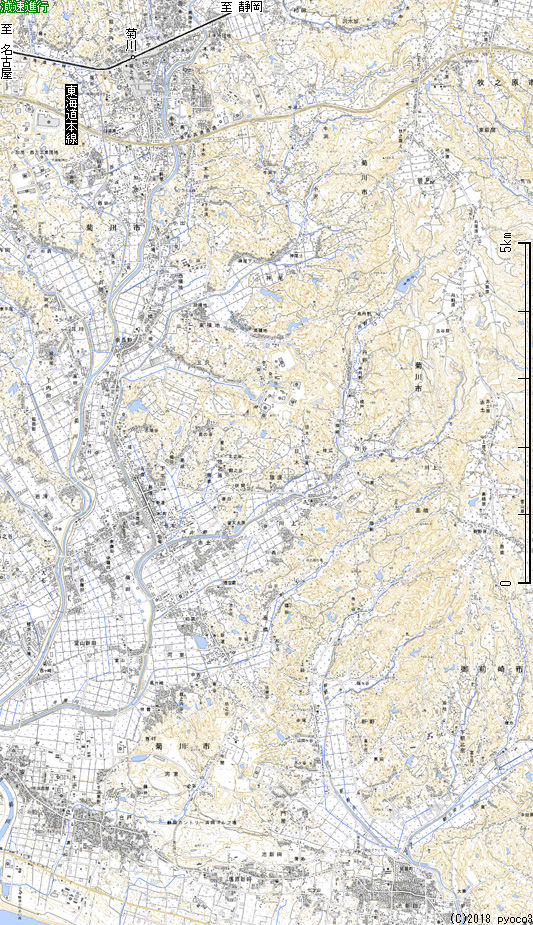
































 掛川
掛川 御前崎
御前崎 掛川
掛川 下平川
下平川 千浜
千浜 御前崎
御前崎